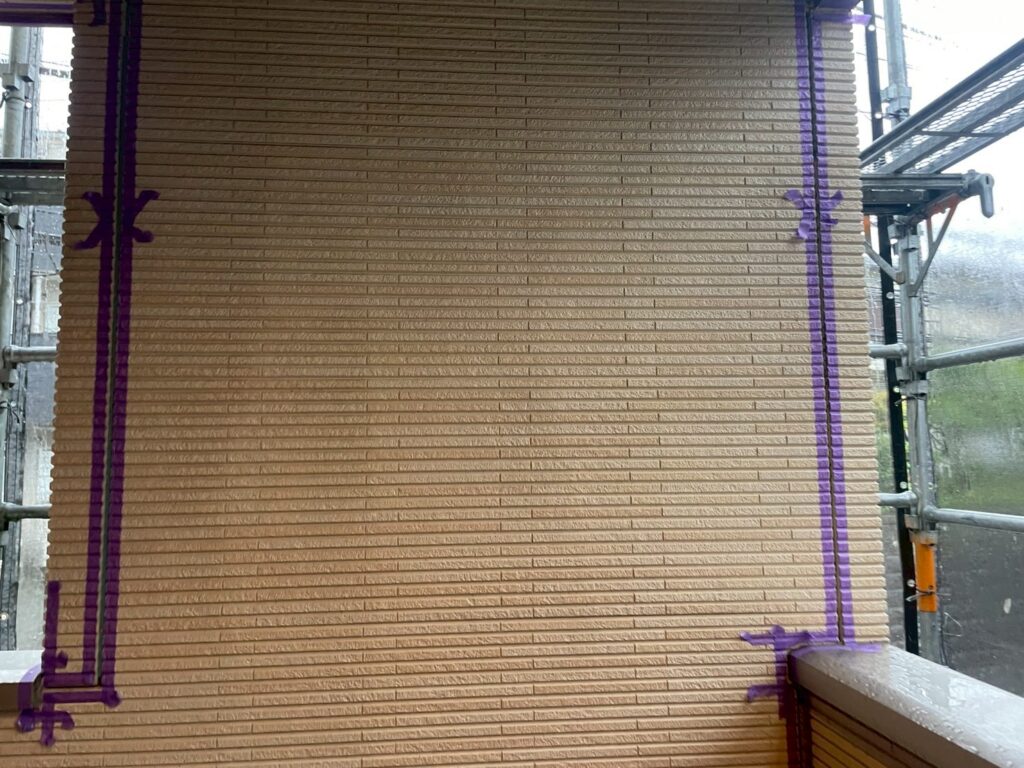陸屋根の防水工事|雨漏りを防ぐ構造とおすすめ工法・費用相場を解説

陸屋根(りくやね)は、フラットでスタイリッシュな外観や屋上活用のしやすさから、住宅やビルなどで多く採用されています。
しかし、勾配が少ない構造のため雨水が滞留しやすく、防水対策が重要です。
この記事では、神奈川の防水工事のプロフェッショナル「大進双建」が、陸屋根が雨漏りしやすい理由や防水工事の種類、費用相場、メンテナンスのポイントを詳しく解説します。
| このコラムのポイント |
|---|
|
陸屋根の防水リフォームを検討している方や、雨漏りが心配な建物オーナーの方はぜひ参考にしてください。
Contents
陸屋根とは|特徴と他の屋根との違い

陸屋根は、傾斜のほとんどない平らな形状の屋根を指します。
一般的には、雨水を流すためにごくわずかな勾配が設けられていますが、外観上はフラットに見えるのが特徴です。
住宅では屋上庭園や物干し場、ビルやマンションでは共用スペースや設備機器の設置場所として利用されることが多く、デザイン性と機能性を両立できる点が大きなメリットです。
一方で、陸屋根は勾配屋根に比べて排水性が低く、水が滞留しやすいというデメリットがあります。
このため、わずかな施工不良や経年劣化でも雨漏りが発生しやすく、適切な防水工事や定期的なメンテナンスが欠かせません。
陸屋根の防水工事やメンテナンスをご検討中の方は、神奈川県の「大進双建」にご相談ください。
現地調査から最適な工法提案まで、専門スタッフが丁寧にサポートいたします。
陸屋根が防水対策を必要とする理由

陸屋根は構造上、ほぼ水平に近い形状のため、水が流れにくく雨水が滞留しやすいという特徴があります。
以下の理由から定期的な防水工事や点検が不可欠です。
- 勾配が少なく水が滞留しやすい
- 防水層が劣化すると即雨漏りに直結する
- 紫外線と温度変化による劣化が早い
勾配が少なく水が滞留しやすい
陸屋根はわずかな勾配しかなく、降雨時に水が屋上面に留まりやすい構造です。
排水がスムーズに行われないため、屋上面には水が残りやすく、防水層の継ぎ目や端部に水分が入り込み、膨れや剥がれなどの劣化を引き起こす原因になります。
また、排水ドレン(排水口)の位置や数が適切でなかったり、落ち葉や砂埃の詰まりで排水機能が低下したりすると、雨水の長時間滞留につながりかねません。
こうした状況が続くと、防水層の膨れ・剥がれが起こり、最終的には雨漏りへとつながるリスクが高まります。
屋上のドレンの詰まりによる雨漏りのリスクについては、こちらの記事でも確認できます。
>関連コラム:屋上ドレンの詰まり放置は雨漏りの原因になる|ドレンの役割や種類も解説
防水層が劣化すると即雨漏りに直結する
陸屋根では、雨水を遮る役割を果たすのは防水層のみです。
勾配屋根のように瓦やスレートで一次防水・防水シートで二次防水といった構造がなく、防水層が劣化すればそのまま室内への浸水につながる点が大きな違いです。
防水層は経年によって収縮・硬化し、細かなひび割れや浮きが発生します。
特に、端部や立ち上がり部分は温度差や動きの影響を受けやすく、劣化の早い箇所です。
小さな損傷でも放置すると、内部の下地に水分が浸透し、建物の構造材や鉄筋を腐食させるおそれがあります。
紫外線と温度変化による劣化が早い
陸屋根の防水層は、常に直射日光や風雨にさらされています。
特に紫外線は樹脂系防水材の分子構造を分解し、ひび割れ・色あせ・弾性低下を引き起こします。
さらに、夏場と冬場の温度差や昼夜の寒暖差による膨張・収縮の繰り返しも、防水層の劣化を早める要因です。
陸屋根の雨漏りや防水層の劣化が気になる場合は、「大進双建」にご相談ください。
状況に合わせた最適な防水工法を提案いたします。
陸屋根に採用されやすい防水工法の種類と特徴

陸屋根の防水には、建物の構造や用途に応じていくつかの工法が採用されます。
代表的なのは以下の3種類です。
- ウレタン防水
- シート防水
- アスファルト防水
いずれも高い防水性能を確保する工法ですが、施工方法・費用・耐用年数・メンテナンス性が異なります。
ここでは、各工法の特徴をわかりやすく比較しながら解説します。
大進双建の防水工事については、こちらでも詳しく解説しています。
<防水工事とは?>
ウレタン防水|複雑な形状にも対応できる柔軟性が魅力
ウレタン防水は、液状のウレタン樹脂を塗布して防水層を形成する工法です。
塗り重ねることで継ぎ目のない一体化した層をつくるため、複雑な形状の屋上や立ち上がり部にも施工しやすい点が大きな特徴です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 施工方法 | 液状樹脂を塗り重ねて防水層を形成 |
| 費用目安(㎡あたり) | 約4,000円〜 |
| 耐用年数 | 約10〜13年 |
詳しいウレタン防水の種類や特徴はこちらの記事で解説しています。
>関連コラム:ウレタン防水の種類|密着工法・シート工法・通気緩衝工法の違いとメリット・デメリット
シート防水|短工期で仕上がる安定した防水性能
シート防水は、塩化ビニル(塩ビ)やゴム製のシートを貼り合わせて防水層をつくる工法です。
工場で生産されたシートを使用するため品質が安定し、施工ムラが少ないのが特徴です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 施工方法 | 塩ビ・ゴムシートを貼り合わせて防水層を形成 |
| 費用目安(㎡あたり) | 約5,000円〜 |
| 耐用年数 | 約10〜20年 |
シート防水の種類と特徴についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。
>関連コラム:シート防水の種類と特徴|メリット・デメリットから工法、メンテナンス方法まで解説
アスファルト防水|耐久性・防水性が高く大型建築向け
アスファルト防水は、アスファルトを熱で溶かしながら複数層に積み重ねて密着させる工法です。
「トーチ工法」「熱工法」などによって層間をしっかりと接着し、非常に高い防水性と耐久性を実現します。
一方で、施工時に熱を扱うため工期や費用はやや高めですが、長期的に見るとコストパフォーマンスに優れる工法のひとつです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 施工方法 | 熱工法・トーチ工法で層を密着形成 |
| 費用目安(㎡あたり) | 約5,500円〜 |
| 耐用年数 | 約15〜20年 |
アスファルト防水の種類やメリットデメリットはこちらの記事で確認できます。
>関連コラム:アスファルト防水とは|種類や工法、メリット・デメリット、劣化症状も解説
陸屋根の防水工事の流れ

陸屋根の防水工事は、現地調査から完了検査まで以下の5つの工程を経て進められます。
- 現地調査・劣化診断
- 既存防水層の撤去または下地処理
- 防水層施工(塗布・貼付けなど)
- トップコート仕上げ
- 最終検査・完了報告
ウレタン防水・シート防水・アスファルト防水のいずれを採用するかで、施工方法や工期が異なります。
ここでは、どの工法にも共通する基本的な施工の流れを紹介します。
現地調査・劣化診断
最初に行うのは、陸屋根の現地調査と劣化状況の診断です。
専門スタッフが表面のひび割れや膨れ、ドレン周辺の詰まりなどを確認し、雨漏りリスクを評価したうえで、必要に応じて散水試験や赤外線カメラによる漏水調査を行い、劣化範囲と原因を正確に把握します。
調査結果を踏まえて、最適な防水工法と施工プランを検討します。
既存防水層の撤去または下地処理
次に、古い防水層の撤去または下地の補修を行います。
防水層が劣化している場合は完全に撤去し、コンクリート下地を研磨・清掃して密着性を高めます。
状態が比較的良好な場合は、既存層の上から施工する「かぶせ工法(オーバーレイ)」を採用することも可能です。
防水層施工
選定した工法に応じて、防水層の施工を行います。
- ウレタン防水:液状の樹脂を複数回塗布し、一体化した防水層を形成。
- シート防水:塩ビやゴムシートを貼り合わせて、均一で安定した防水面をつくる。
- アスファルト防水:加熱したアスファルトを積層し、高い密着性を確保。
いずれも、塗布ムラや気泡を防ぐ施工技術が重要です。
防水層の厚みや塗り重ね回数などは仕様書に基づいて管理されます。
トップコート仕上げ
防水層の上には、紫外線や摩耗から保護するトップコートを塗布します。
この仕上げ層が防水層を直射日光や雨風から守り、耐用年数を延ばす役割を果たします。
トップコートは経年劣化しやすいため、3〜5年ごとの再塗装が必要です。
最終検査・完了報告
最後に、仕上がりと排水機能を確認し、勾配不良やドレンの詰まりがないかを点検します。
雨水の流れも確認したうえで、施工後は写真付きの完了報告書を提出し、保証書を発行します。
大進双建の防水工事の流れの流れについてはこちらのページで紹介しています。
<工事までの流れ>
陸屋根の防水を長持ちさせるメンテナンス方法

陸屋根の防水を長持ちさせるためのメンテナンスは、以下のような日常管理と定期点検が効果的です。
- 排水ドレンを清掃し、詰まりを防ぐ
- 屋上に重量物・植物を置かない
- 3〜5年ごとにトップコートを塗り替える
- 定期点検を10年ごとに実施する
小さな汚れや詰まりでも、放置すれば防水層の劣化や雨漏りにつながるおそれがあります。
特に排水ドレンの清掃とトップコートの再塗装は、低コストで効果の高いメンテナンスとしておすすめです。
陸屋根や屋上の防水工事をご検討中の方は、神奈川県の「大進双建」にご相談ください。
多くの防水工事実績で培った技術力を活かし、ていねいで耐久性の高い仕上がりをご提供いたします。
陸屋根の防水工事を行う際の施工会社を選ぶポイント

陸屋根の防水工事は、建物の構造を深く理解し、確実な施工技術を持つ業者に依頼することが重要です。
防水層は施工精度によって性能が大きく左右されるため、価格だけで判断せず、実績と信頼性を重視して選びましょう。
業者を選ぶ際は、次のようなポイントを参考にしてみてください。
- 陸屋根や屋上防水に実績がある会社を選ぶ
- 自社施工・保証対応の有無を確認する
- 劣化診断から改修提案まで一貫対応できる業者を選ぶ
特に、陸屋根は排水性が低く、一般的な屋根よりも施工難易度が高いため、同様の現場経験が豊富な業者を選ぶことが大切です。
防水工事のことなら「大進双建」にお任せください!

陸屋根は、デザイン性や屋上活用のしやすさなど多くの利点がある一方で、排水性の低さから防水トラブルが起こりやすい構造です。
定期的な点検やトップコートの塗り替え、排水ドレンの清掃など、計画的なメンテナンスが欠かせません。
また、建物の規模・構造・用途によって最適な防水工法は異なります。
それぞれの特徴を理解し、条件に合った工法を選ぶことで建物の長寿命化が可能になります。
防水の状態は目視だけでは判断が難しい場合もあるため、専門業者による診断と適切な提案を受けましょう。
監修者情報

- 株式会社大進双建 代表取締役
-
17歳から防水工事・外壁修繕の現場で実務を開始し、大手下請け会社や官公庁工事に携わる。
8年の実務経験を経て独立後、年間30件以上の大規模修繕工事を手掛ける。
住宅、アパート、倉庫などの防水・塗装工事においても豊富な施工実績を持つ。
一級建築施工管理技士
一級ウレタン塗膜防水施工技能士
一級シーリング防水施工技能士
一級塩化ビニルシート防水施工技能士
一級アスファルトトーチ防水施工技能士
最新の投稿
- 2026.01.20防水工事マンション廊下の防水シート工事とは|長尺シート施工を事例で見る特徴と工事の流れ
- 2026.01.05防水工事ベランダ塗装の剥がれ補修|放置すると起きるリスクと正しい直し方
- 2025.12.20防水工事パラペット防水とは|雨漏りを防ぐポイントと劣化のサインや改修方法を解説
- 2025.12.05防水工事ベランダの排水溝のつまりの原因と解消方法|専門業者に依頼すべきケースやメンテナンス方法も紹介