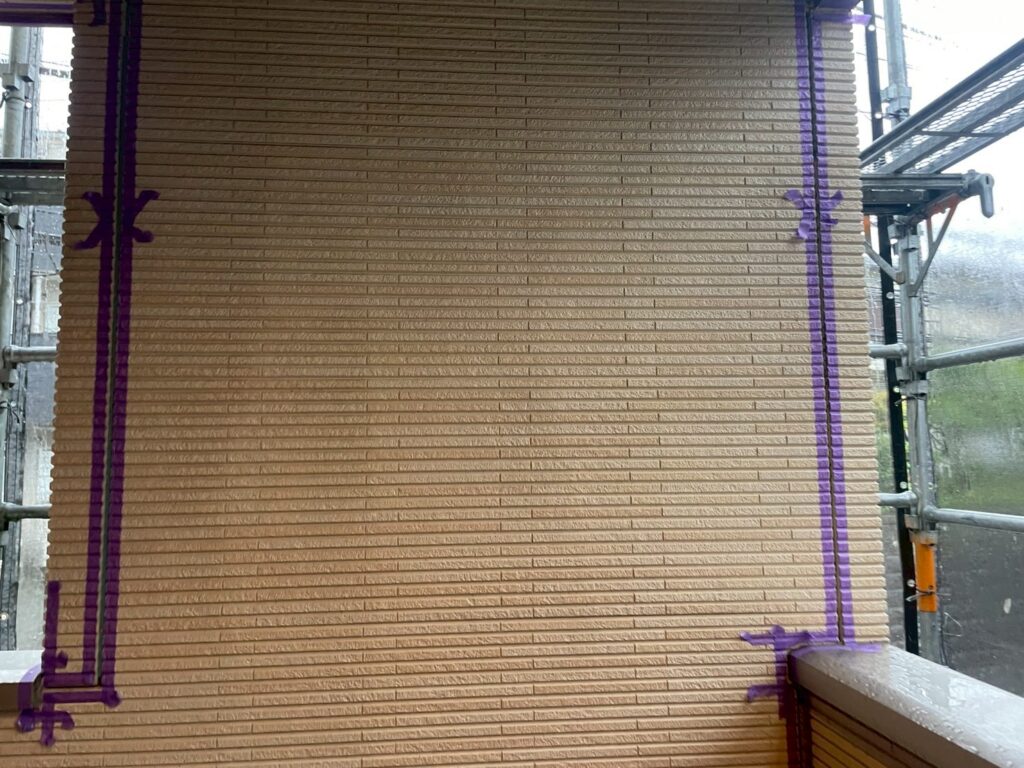鉄筋コンクリートの屋上で雨漏りする原因と補修方法|雨漏り原因の見つけ方も解説

ビルやマンションなど鉄筋コンクリート造の建物は耐久性が高いイメージがありますが、屋上から雨漏りするリスクもあります。
万が一屋上から雨漏りが発生した場合、なるべく迅速に原因を特定し、適切な対策をすることが大切です。
そこでこの記事では、神奈川の防水プロフェッショナルである「大進双建」が、鉄筋コンクリートの屋上でよくある雨漏りの原因と補修方法をセットで解説します。
雨漏りが発生したときの原因の見つけ方も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
| このコラムのポイント |
|---|
|
Contents
鉄筋コンクリートの屋上で雨漏りする原因と補修方法
まずは、鉄筋コンクリート造の建物の屋上から雨漏りする原因について、よくあるパターンをピックアップしてご紹介します。
よくある原因を把握しておけば目視点検などで雨漏りを予防しやすくなり、原因の特定にもつながります。
防水塗膜の劣化や剥がれ

鉄筋コンクリート造の屋上は基本的に防水工事をしますが、塗膜の劣化や剥がれなどが原因で雨漏りするケースが多いです。
屋上防水の施工方法はさまざまですが、紫外線や風雨などで徐々に劣化し、耐用年数を過ぎると防水性能が低下して雨水が染みこむ原因になります。
【補修方法】⇒点検と防水工事のやり直し
屋上の防水塗膜の劣化が雨漏りの原因の場合は、まず全体を点検して適切な補修をした後、防水工事を再施工する必要があります。
屋上防水にはいくつかの種類があり、下地の状況や予算などに合わせて選ぶことが大切です。
こちらのコラムで、屋上防水の種類や費用相場について詳しく解説しています。
>関連リンク:屋上防水の種類と選び方|メリット・デメリットから費用相場も解説
コーキングの劣化

屋上の立ち上がりや笠木部分などにシリコンのコーキングが使われている場合、経年劣化によりすき間が空いて雨漏りの原因になることもあります。
コーキングは年数が経つと徐々に痩せていき、亀裂や剥がれが発生してすき間から水分が染みこむ原因になります。
コーキングの種類や状況にもよりますが、一般的には5~10年前後が寿命の目安です。
【補修方法】⇒コーキングの打ち替え
コーキングのすき間から雨漏りしている場合は、一度シリコンの充填剤を撤去して打ち替えで補修するのが一般的です。
既存のコーキングの上から「増し打ち」する方法もありますが、劣化が早くなり雨漏りが再発するリスクがあるため、一度撤去して打ち替えするのが基本です。
増し打ちの方がコストや工期を抑えられますが、屋上のコーキングは特に防水性に関わるポイントなので基本的には避けましょう。
コンクリートのひび割れ

乾燥収縮や地震による揺れによってコンクリートにひび割れが発生し、すき間から雨漏りするパターンも代表的な原因の1つです。
ヘアクラックと呼ばれる髪の毛程度のひび割れは雨漏りの原因となるリスクは少ないですが、幅が広く深い構造クラックの場合は注意が必要です。
コンクリート内部まで雨水が浸透すると、雨漏りの原因になるだけでなく、内部の鉄筋が錆びて建物に致命的なダメージが発生するリスクもあります。
【補修方法】⇒専用の材料でクラック補修する
コンクリートクラックによる雨漏りの場合、状況に合わせて適切な工法や専用の補修材で対策する必要があります。
クラックの幅が広く深い場合は、Vカット工法で溝をつくり、シーリング材やモルタルで補修するのが一般的です。
また、強度に影響があるクラックが発生している場合は、専用の補修材を注入して強度や耐久性を回復させる方法もあります。
コンクリートクラックによる雨漏りはなるべく早めに専門家の診断を受け、適切な対処をすることが大切です。
排水ドレンの劣化や詰まり

屋上に設けられた排水ドレンが劣化してすき間ができたり、詰まったりすると雨漏りの原因になることが多いです。
屋上の雨水は勾配に沿って排水ドレンに集まるため、すき間があったり詰まってスムーズに流れなかったりすると、雨漏りに直結します。
落ち葉やホコリなどがドレンに詰まって排水不良を起こすケースもあります。
【補修方法】⇒定期清掃とドレン改修
まず、雨漏りを予防するためにはドレンの定期清掃が重要です。
屋上全体の清掃でドレンに落ち葉やゴミが流れ込むのを防ぎ、排水部分をふさがないように取り除きましょう。
ドレン自体の劣化ですき間が発生している場合は、改修用ドレンで補修します。
こちらのコラムで改修用ドレンについて詳しく解説しています。
>関連リンク:改修用ドレンは防水工事に欠かせない|役割や設置方法、メリットまで解説
オーバーフロー管の施工不良や詰まり

屋上に設けられているオーバーフロー管が正しく設置されていなかったり、ゴミで詰まっていたりすると雨漏りの原因になることがあります。
オーバーフロー管とは大雨などで雨水を処理しきれなくなった際、一時的に外部へ排水するための経路のことです。
高さや角度などが正しく設けられていないと、オーバーフロー管からの排水がうまくいかず台風など雨量が多いときに雨漏りするケースがあります。
【補修方法】⇒オーバーフロー管の点検と改修
オーバーフロー管が原因で雨漏りしている場合は、正しく設置されているか、詰まりがないかなどの点検を行います。
そもそもオーバーフロー管が足りなかったり正しく設置されていなっかったりする場合は、再施工が必要です。
パラペットや笠木からの浸水

屋上のパラペットの立ち上がり部、笠木のすき間が雨漏りの原因になることも多いです。
パラペットとは屋上の外周に設けられた壁のことで、床面との接合部分にすき間ができて雨漏りするケースがあります。
また、パラペットの上に笠木が設けられている場合、コーキングのすき間やビス穴から雨水が侵入することもあります。
【補修方法】⇒防水補修やコーキングやり直し
パラペットの立ち上がり部のすき間やひび割れから雨漏りしている場合は、防水補修を行います。
笠木が原因で雨漏りしているケースでは、一度取り外して内部を点検し、つなぎ目やビス穴のコーキングをやり直す方法が一般的です。
コンクリートの屋上雨漏りの診断・補修は、防水工事専門の「大進双建」にご相談ください。建物の状況を総合的に判断し、原因を突き止め適切な補修方法をご提案いたします。
コンクリート屋上の雨漏り箇所の見つけ方は?

ここまで見てきたように、鉄筋コンクリート造の建物の雨漏りにはさまざまなパターンがあり、原因を特定する難易度は高いです。
実際に、コンクリート屋上の雨漏り箇所を見つける方法をご紹介します。
雨漏りのリスクが高い場所を点検する
まずは雨漏りしている箇所の周辺から、前述したリスクが高い場所を目視点検します。
床面の防水層や排水ドレンなど、劣化して雨漏りの原因になりそうな場所をリストアップし、後述する調査方法を実施します。
雨漏りは横方向の構造体を伝って大きく移動することもあるため、室内で濡れている場所の真上だけではなく、屋上全体をチェックすることが大切です。
雨漏りしている場所に水をかけて調べる
雨漏りが発生している場所の近くに直接水をかけて、場所を特定するのが一般的な調査方法です。散水調査と呼ばれることもあります。
雨の状況を再現することで、雨漏りの原因を確実に特定しやすいのが散水調査のメリットです。
ただし、状況によっては大量の水が必要になり、時間がかかるケースもあります。
赤外線カメラで調査する
雨漏り箇所の表面温度を赤外線カメラで撮影し、雨水の侵入口を推測する方法もあります。
雨水が流れた場所は周辺より温度が低くなるケースが多く、目視できない場所の雨漏りを発見しやすいのが特徴です。
ただし、雨漏りを直接確認できるわけではないため、あくまで推測であることに注意が必要です。
天井裏などを目視で確認する
天井に点検口などが設けられている場合、雨漏りしている場所の天井裏を目視確認する方法もあります。
雨が流れた痕跡を発見できれば原因を特定しやすくなり、適切な補修方法を選択できるのがメリットです。
点検口がなく直接目視するのが難しい場合は、スコープカメラなどを使って照明器具の取付穴などから点検する方法もあります。
コンクリートの雨漏りを放置するとどうなる?

鉄筋コンクリート造のビルやマンションで屋上からの雨漏りを放置すると、建物への重大なダメージや漏電・火災などにつながるリスクがあります。
クラックが原因で雨漏りしている場合、雨水がコンクリート内部の鉄筋に達すると徐々に錆びてしまいます。
錆びた鉄筋はコンクリートを内部から押し出し、「鉄筋爆裂」が発生して構造が破損する原因に。
軽微な爆裂は補修できるケースもありますが、症状が進行すると建物への重大なダメージになり、耐震性に影響するリスクも考えられます。
また、屋上から侵入した雨水で電気配線がショートし、漏電火災につながるケースもあります。
ちょっとした雨漏りでも天井裏で被害が広がっていることもありますので、なるべく早めに専門家の点検や診断を受けましょう。
コンクリートの屋上雨漏りはDIY補修できる?

コーキングや防水塗料などの補修材はホームセンターなどでも手に入るため、コンクリートの屋上雨漏りをDIY補修できないか検討する方も多いようです。
結論としては、鉄筋コンクリート造の建物の屋上雨漏りは、DIY補修ではなく防水工事のプロに相談するのがおすすめです。
前述したように屋上雨漏りの原因はさまざまで、一ヵ所補修しただけでは直らないケースも少なくありません。
また、雨漏りの原因特定は難易度が高く、一般の方が適切な補修方法を選定するのは難しいです。
せっかく補修をしても、適切な方法でないと雨漏りが止まらなかったり、すぐ再発したりする可能性もあります。
こちらで屋上防水のDIY施工について解説していますので、あわせてごらんください。
>関連リンク:屋上防水を自分でやるのは危険|メリット・デメリットや費用削減の方法を解説
防水工事のことなら「大進双建」にお任せください!

鉄筋コンクリート造の屋上から雨漏りする原因は複数あり、なるべく迅速に適切な補修方法をとることが大切です。
少しの雨漏りでも放置せず、なるべく早めに防水工事・補修の専門家に相談しましょう。
神奈川・東京・千葉・埼玉の防水工事なら「大進双建」にお任せください。
雨漏りの状況に合わせて適切な補修方法をご提案いたします。
監修者情報

- 株式会社大進双建 代表取締役
-
17歳から防水工事・外壁修繕の現場で実務を開始し、大手下請け会社や官公庁工事に携わる。
8年の実務経験を経て独立後、年間30件以上の大規模修繕工事を手掛ける。
住宅、アパート、倉庫などの防水・塗装工事においても豊富な施工実績を持つ。
一級建築施工管理技士
一級ウレタン塗膜防水施工技能士
一級シーリング防水施工技能士
一級塩化ビニルシート防水施工技能士
一級アスファルトトーチ防水施工技能士
最新の投稿
- 2026.01.20防水工事マンション廊下の防水シート工事とは|長尺シート施工を事例で見る特徴と工事の流れ
- 2026.01.05防水工事ベランダ塗装の剥がれ補修|放置すると起きるリスクと正しい直し方
- 2025.12.20防水工事パラペット防水とは|雨漏りを防ぐポイントと劣化のサインや改修方法を解説
- 2025.12.05防水工事ベランダの排水溝のつまりの原因と解消方法|専門業者に依頼すべきケースやメンテナンス方法も紹介